こんにちは。
この記事ではがんは遺伝で決まるのか。がん家系はあるのか。
というお話をしていきます。
ですがその前に、遺伝子・DNA・ゲノムといった、「聞いたことあるけどよくわからない」という人が多い言葉について
簡単に説明をさせてください。
遺伝子・DNA・ゲノム
遺伝子
「遺伝子」は人間の体を作るために必要な設計図です。
人間の体はたくさんの「細胞」から成り立っています。
たとえば、筋肉は筋肉の細胞から、骨は骨の細胞からできています。
血液や脳もすべて細胞です。
形も働きも異なるたくさんの細胞が互いに協調して働くには、正確な「設計図」が必要です。
その設計図となるのが、「遺伝子」です。
また、遺伝子の役割はアミノ酸を繋げる為の設計図でもあります。
DNA
遺伝子と聞くと思い浮かぶのがDNAですが、
DNAは遺伝子の本体となる物質です。遺伝子の情報にそってタンパク質が作られます。
DNA(デオキシリボ核酸)は、4種類の物質が長く連なってできています。
この物質の並び順は、それぞれを構成する塩基の頭文字A、T、G、Cで表した「文字列」で表すことができます。
この文字列のことを「塩基配列」といいます。
遺伝子の情報は塩基配列によって決まり、その情報に従って体内で「タンパク質」が作られます。
タンパク質は細胞を作る材料になります。
また、細胞の中で直接働いているのも、遺伝子ではなくタンパク質が中心です。
遺伝子を設計図とすると、タンパク質はその設計図によって作られる「材料」や「道具」ということができます。
正しい時期に正しい場所で、正しいタンパク質が作られることで、人間の体は成り立っているのです。
ゲノム
ゲノムという言葉も耳にすることがあると思います。
「DNAの文字列に表された遺伝情報すべて」をゲノムといいます。
ゲノムの中でも「タンパク質」の設計図の部分が「遺伝子」です。
ゲノムとは「DNAの文字列に表された遺伝情報すべて」のことです。
ヒトゲノムのDNAの文字列(塩基)は30億文字列(塩基対)にもなります。
この30億文字列のうち、タンパク質の設計図の部分を「遺伝子」とよんでいます。
ヒトゲノムには約25,000個の遺伝子が含まれています。
人間の体重の1/20ぐらいのネズミにも遺伝子は約25,000個あります。
遺伝子の数というのは体の大きさに左右されず生きていくために必要な遺伝子の数というのは同じぐらい必要となってきます。
遺伝子についての説明も終わりましたので本題に移ります。
がん遺伝子はある
がんは遺伝で決まるのか。がん家系はあるのか。
についてですが、
がん遺伝子はあります。
がん遺伝子があったらがんになりやすいのかと思われるかと思いますが、
がんを抑制する遺伝子もありますので、その遺伝子が働けばがんを抑えつけてくれるので問題ありません。
ゲノム全体の中に遺伝子があり、遺伝子の中にはがんに関係する部分もあるしそれを抑え込んでくれる部分もあるということが分かってきたのでがんと遺伝子は関係がある。ということが分かってきたのです。
がん遺伝子があってもがん遺伝子を抑え込む遺伝子があるのであればがんにならないのではないか?
と、思われた方も多いかと思いますが、先程の約25,000個の遺伝子ですが全ての遺伝子を体が使っているわけではありません。
遺伝子として持っていても使う場合もあれば使わない場合もあります。
ですので、抑制する遺伝子が働かないこともありますし、がん遺伝子が働かないということもあります。
がん遺伝子は環境に左右される?
では、何が原因でがん遺伝子が働いたり働かなかったりするのでしょうか。
それは、環境が影響しているのではないかと言われています。
必ず病気になるマウスを作ることができて、そのマウスの環境を変えてやるとどうなるのかという実験が行われました。
その結果、普通に育てたマウスは病気になってしまいましたが、餌などの環境に気を付けて育てたマウスは健康に育ったという実験結果が出ました。
人間の場合どうなったかというと、前立腺がんと診断された方がいらっしゃいました。
その方はがんと診断されてから食生活と生活様式の見直しを行いました。
暫くして遺伝子分析を行うと500以上の遺伝子活性が切り替わり、
遺伝子的に発現していたものが発現しなくなりました。
更にその大半ががんと関係するものだったのです。
がん家系だから、遺伝だから必ずがんになると言うわけではありません。
リスクとして十分に気を付けていれば遺伝子があっても発現しない事もあります。
ただただ怖がるだけではなく、普段からの食事や生活に気を付けることが大切なのです。
しかし、逆を言えばがん家系でない方でも偏った食事や不健康な生活を行っているとがん遺伝子が発現してがんを患ってしまうかもしれませんので油断は禁物です。
強い信念を持って自分自身の行動を変えていきましょう。

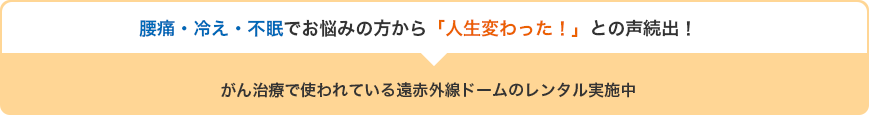
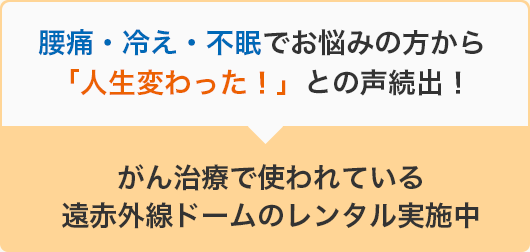

コメント