低体温・低酸素という言葉を聞いたことがありますか?
人間の体温は36.5℃以上が理想とされています。
しかし現在は35℃台の方も珍しくありません。
また、低酸素は血流が悪くてしっかり体中に酸素が行き渡っていない状態です。
この低体温・低酸素が「がん」とどう関係があるのか、お伝えしていきます。
低体温・低酸素になる
低体温・低酸素になってしまう自然な環境というと山に登ることです。
高い山に登ると気温は低くなりますし、酸素も薄くなってしまうので
低体温・低酸素状態になって倒れてしまう人もいていますし、
高山病という病気にもなってしまいます。

では、高いところに住んでいる人や、登山家の人、最近では高地トレーニングを行ったりしている人はどうなのでしょうか?
そのような人たちは身体全身で低体温・低酸素状態に慣れていきますので鍛えられていきます。
しかし身体の中で部分的に低体温・低酸素状態になってしまうこともあります。
例えば体の臓器の中で心臓や肝臓・腎臓は特に大切な臓器なのでずっと機能させ続けないといけません。
そのために糖分や酸素を優先的に使えるように血流を変える必要があります。
体の中の血液の量は決まっているので、心臓に優先的に血液を送ると他の臓器への血液の供給量は減ってしまい一時的に低体温・低酸素状態になってしまいます。
これは日常的にあることで問題はありません。
では、がん患者さんが低体温・低酸素状態になるのは良くないと言われていますがどうしてなのでしょうか。
ワールブルグ効果
オットー・ワールブルグというドイツのお医者さんががん細胞の研究をしていて、
「がん細胞は酸素が十分に存在してもブドウ糖の取り込みと解糖系が亢進し大量の乳酸が産生されミトコンドリアでの酸素呼吸が制御されている」ということを発見しました。
これをワールブルグ効果と言います。
ミトコンドリアというのはエネルギーを出す細胞のエンジンみたいなもので、酸素を使い細胞全体を動かしている器官です。
しかし、がん細胞の中にあるミトコンドリアは酸素を使わずにブドウ糖をたくさん使います。
ブドウ糖をエネルギーの要素にするエンジンがあり、それを解糖系と言います。
通常であればミトコンドリアと解糖系の両方を使うのですが、がん細胞はミトコンドリアを使うのを嫌がっている、というのが現在も定説となっています。
人間の体のシステムでは必要なところに血液を送るために
血管を広げたり縮めたり、血圧を上げたり下げたりしているので
血液は均等ではないので一時的な低体温・低酸素は大きな問題ではありません。
しかし、慢性的なストレスや偏った食事をして細胞に必要な栄養素を供給できなくなってしまいます。
このように部分的な厳しい環境になってしまった場合、
体内で特別な酵素が作られて調整するのですが、
厳しい環境が長く続くと酵素が作られなくなり調整ができなくなってしまいがん細胞が好む環境へとなってしまします。
このような環境に適応してがん細胞ができてしまった、というのがワールブルグ効果からの考え方となります。
「低体温・低酸素だからがんになる」
のか、
「がん細胞が低体温・低酸素の環境を好むからそうなる」
のか、どちらが先なのかはわかっていません。
ですが、長期的な低体温・低酸素にならない為に食生活の見直しや慢性的なストレスを緩和できるよう心がけていきましょう。

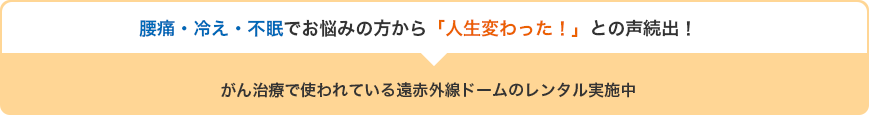
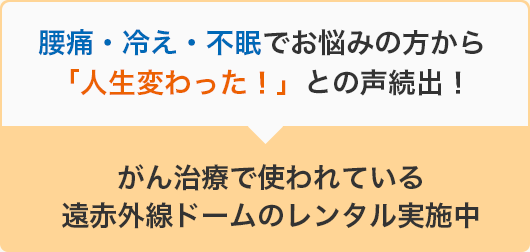
コメント